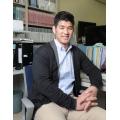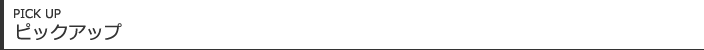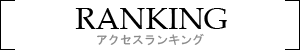十二歳のときだった。
夜中に目覚めたら、父親が馬乗りになって
包丁の刃を自分に向けていた――。
そんな壮絶な少年時代を生き抜くことができたのは、
「人を笑わせる」喜びがあったからだ。
いまや、〝上方の爆笑王〟と形容される五五歳。
一〇〇〇人を超す大ホールで、身振り手振りも華やかに、
機関銃のような勢いで語り、笑いの渦を巻き起こす。
夢は二〇二〇年、日本武道館での還暦独演会である。

木村政雄編集長スペシャルインタビュー
桂 雀々 落語家
木村☆お久しぶりですね。私が初めてお見かけした雀々さんは、まだ詰襟の学生服姿で、桂枝雀さん(故人)に付いて、テレビ局に来られていた頃ですね。
桂☆そうですか。僕が初めて木村さんを意識したのは、実は小学校六年生のときなんですよ。
木村☆え、そんなに前からですか?
桂☆天才漫才コンビやすしきよしの横山やすし師匠(故人)が問題を起こされて謹慎になって、西川きよし師匠が一人で活動されていたときです。小学生の僕は、関西テレビのある番組の会員になって、スタジオ見学によく行っていました。会員番号は忘れもしない二七〇九一番。生放送の合間の休憩時間に、きよし師匠に寄り添っておられる若き敏腕マネージャーのお姿を、いまもはっきり覚えています。少しも変わっていらっしゃいませんね。
木村☆いえいえ変わりましたよ、もう六九歳ですから……。その番組って、関西テレビの子ども向けバラエティ『四時だぜ!飛び出せ!!わいわいワイド』じゃないですか?
桂☆そう、それです。スタジオ見学ができる生番組で、桑原征平アナが本番までの時間を繋ぐために、見学に来た子どもをステージに上げて何か芸をさせるんです。僕は歌手の西城秀樹さんと一緒にオープニングの歌を歌わせてもらって、人前で笑いを取る面白さを知ったんです。それと、きよし師匠が楽屋入りされるとき着ておられた革のコートが七〇万円とか桑原アナが話しておられて、「うわー、芸能界で売れると、こうなるんだ!」と。貧乏のどん底にあった僕には、ものすごいインパクトがありました。
木村☆雀々さんといえば、十一歳でお母さんが蒸発、十二歳でお父さんも家出……。お書きになった『必死のパッチ』を読み返したんですが、少年時代の過酷な暮らしぶりに改めて胸が詰まりました。タイトルの〝必死のパッチ〟は関西独特の言い回しで、一生懸命の百倍?というか、命がけでがんばるというような意味ですよね。それにしてもよくがんばりましたよね。
桂☆親がいなくなった一番大変なときに、僕はテレビ局できよし師匠や木村さんを見て芸能界にあこがれを持ちました。この無敵のポジティブ思考は、どうも蒸発した母親のDNAを受け継いだ結果らしいんですけど(笑)。
木村☆たしか、お父さんは、うどん屋さんを営んでおられたんですよね。
桂☆行列ができるほど評判のいい屋台で、売り上げは一日何万円もあったそうです。真面目に働けば、まともな暮らしができたのに、親父は仕入れの帰りに住之江競艇場に行って、すっからかんになって帰ってくる。おまけに毎週、週末には、市営住宅のわが家に二〇人から三〇人のおじさんたちが集まってバクチを打つんです。当然、借金まみれの生活でした。
木村☆いまだったら、すぐに警察に通報されるでしょうに。
桂☆のんきな時代というか、ま、僕は一人っ子だから自由奔放に、引きこもりにもならずに済みましたけどね。
木村☆お母さんが蒸発された後、お父さんは借金取りに追われる毎日を悲観して、雀々さんを道連れに無理心中を決行しようとされたんですよね。夜中にお父さんに包丁を突きつけられたというのは本当ですか?
桂☆ホンマの話です。夜中、胸が重苦しくて目が覚めたら、親父が包丁を持って、僕の上に馬乗りになって「すまん。もうあかん! ワシも死ぬからオマエもワシと一緒に死んでくれ」って。驚いて「イヤや! 僕は生きたいねん!」と叫んだら、親父は「オマエ生きるんやろ? ほなこの家から出た方がええぞ。ワシはとりあえずここから出る」そう言って、翌朝出ていきました。中学校の入学式が終わって間もない頃でした。
木村☆それから一人で、どうやって生活したんですか。
桂☆近所の方々が手を差しのべてくださり、僕を何とかグレさせんように支えてくれたんです。大阪の下町の我孫子という町で、町内全体が「児童施設」のように温かいんです。情があって、やさしさ満載で、親代わりみたいで、おばちゃんたちが弁当を作ってくれたり、学費を補填してくれたりして、おかげで何とか食べることには不自由しませんでした。
木村☆いくら近所の方が親切だといっても、中学一年生って、まだ子どもじゃないですか。それがここまで立派になられたのは奇跡に近いですよ。
桂☆当時、大はやりだったテレビ・ラジオの素人参加型番組に出ていたことが、僕の救いになったんだと思います。人前で笑いを取る快感に目覚めて、グレてる場合じゃないなと思いました。それに、生活のためにバイトもしないといけない。朝夕の新聞配達に、夜は近所の洋食屋で皿洗いや出前持ちをして、バイト代の代わりに晩御飯を食べさせてもらう。親がいないので、思春期の友達が親に見せられないような本やらタバコを持って遊びに来るのはいいんですが、日暮れになると電気が点かないのが恥ずかしい。そんなとき毎日放送の『素人名人会』で「参加賞」一万円をもらい、家賃や電気代を払ってほっとしたものです。「名人賞」をもらったときには、もう大富豪の気分。賞金三万五〇〇〇円ですからね。まあ、無責任な両親のおかげで、生活力は身につきました(笑)。

借金取りが泣いた!
十四歳、一世一代のひとり語り
木村☆『必死のパッチ』の中で、借金取りが、雀々さんのためにお金を置いて帰ったエピソードは泣けましたね。
桂☆父親が出ていってからも、「親父の居場所を教えろ」と毎日借金取りがやって来ました。三人組で、夜の十一時半頃、夜中の二時前、明け方と三回も来るんです。玄関扉を蹴破って、土足でどかどか上がってくる。布団の中の僕を引きずり出して「ええかげんに言え!」と胸倉をつかむ。子どもながらに精神的に追い込まれていたんでしょう。何回目かのときに「知らんものは、知らんのです」と、取り立てのリーダーの目をまっすぐ見て言ったんです。そのとき、この人はええ人やと直感して、両親とも家を出たこと、電話もガスも電気も止められ、真っ暗闇の中で一人で暮らしている寂しさなどを訴え、涙ながらに「助けてください!」とすがったら、その借金取りは目に涙を浮かべ、「お前、明日生活する金あらへんやろ? 少ないけど取ってけ」言うて、五〇〇〇円を僕の手に握らせて帰っていったんです。それから二度と、借金取りたちは現れませんでした。中学二年生の僕は一世一代のしゃべりによって窮地を脱し、おまけにギャラまでもろたんですわ(笑)。あの涙もろい、小太りの兄ちゃんには会ってみたいですね。
木村☆学校は、ちゃんと通ったんですか。
桂☆学校は憩いの場でしたから休まず通いました。先生方も事情を知っているようで、大人たちは、僕がいつ暴発するんやないかと、ハラハラして見守っていたようです。やはり、笑いが身を助けてくれたんやなと思います。
木村☆自分にはそういう才能があるということに、いつ頃から気がついたんですか。
桂☆『わいわいワイド』で、素人が何か変なことを言ったり変な動きをすることで笑いがとれる、その面白みを味わったときでしょうね。漫才の花紀京さんや岡八朗さんの掛け合いとかを子どもながらに分析して、絶妙の「間」によって笑えるんやと気づいたんです。あのとき、僕の生き方の矢印が、「笑い」の方にピタッと定まったんです。
木村☆関西では、勉強やスポーツができる子より、「おもしろい子」がいちばん評価されますからね。
桂☆「おもろいやつは吉本へ行け」が決まり文句、ほめ言葉ですよね。中学一年のときに、バラエティ番組の『パクパクコンテスト』(よみうりテレビ)というのがあって、山本リンダさんや西城秀樹さんの当て振りをして小遣い稼ぎをしていました。
木村☆東京の『ぎんざNOW!』 (TBSテレビ)も出たんですよね。
桂☆中学三年のときですね。高知県の親戚の家に遊びに行っていたとき、たまたまオンエアされていたんです。こんな「しろうとコメディアン道場」があるなら、是非出たい。けど普通に申込書を送るより、積極的に直談判しようと一〇四で電話番号を調べて、『ぎんざNOW!』の担当者に交渉したんです。「交通費も要りませんから何とかお願いします」と頼み込んで、予選も無しに出演させてもらったんですよ。五週勝ち抜くとチャンピオンになってレギュラー出演できるんですが、トントンと五週勝ち抜いて「六代目チャンピオン」になって、交通費も出してもらえました。
木村☆すごいプレゼンテーション能力があったんですね。
桂☆気持ちは入っていたと思います。僕の場合、切羽詰まっていますから。いろいろ事情を話して「どうか、お願いします!」って。丸坊主で、Tシャツにオーバーオールの大阪弁の子どもは、当時の東京では、なじみが無かったと思うんです。その審査員の中に、お笑い界の伝説のプロデューサー澤田隆治さんがおられ、その後もずっとお付き合いをさせてもらったんですよ。
木村☆どんな困難なときも、他人を頼らないで道を切り開いていく、すごいパワーですね。
桂☆ダメでもともと、自分が言わないことには何も前に進まない――いまでもそれでやっています。
木村☆『必死のパッチ』の中に、「心まで貧乏になったらあかん」という一節がありました。素敵な言葉ですよね。普通だったら、めげてしまうような環境の中で、他人のせいにもせず、まっすぐに進んでいったわけですね。
桂☆そういう環境が僕を強くしたというか、やっぱり、母親のDNAもあるでしょうね。十一歳で生き別れた母親が一二年前に突然、僕の前に姿を現したんですよ。記憶の中の母は細くて折れそうだったのに、いまやふくよかな巨体を豪快に揺すって笑う、やり手の起業家になっていました。今年八二歳ですが、まだまだ元気でやっています。

伝説の天才落語家・桂枝雀のもとで
ダイナミックな話芸を磨く
木村☆落語家を目指そうと思ったのはどのタイミングなんですか?
桂☆十四歳のときに、夜のラジオを聴いていたら、桂きん枝師匠の落語「狸賽」が流れてきて、面白かったんです。たまたま録音していたので書き起こして覚え、見よう見まねで練習。教室でやってみると、すごく受けたんです。「これや!」と思いました。それで今度は、同じネタを素人参加番組にかけてみようと応募したら、オーディションに合格してチャンピオンになって、大入り袋を一二枚、一万二〇〇〇円いただいて、そこで自信がついたんです。そのとき「ええもん見つけた」と思いました。漫才やったら相方が要る、新喜劇やったら団体に入らなあかん。落語は一人でできる。よくも悪くも全部自分の責任でやれる。そうこうしているうちに、うちの師匠の番組があって、たまたまそこに出ることになったんです。
木村☆〝伝説の天才落語家〟桂枝雀さんとの出会いですね。
桂☆それまでにも師匠の落語は聴いて知っていたんですが、そのときは何より、存在があたたかい、この人なら僕の面倒をみてくれる、安らぎがあると確信したんです。きっと三年間、電気も無いような家で一人で暮らして、精神状態が不安定だったんですね。だから中学卒業後、安らぎを求めて駆け込み寺みたいな感じで枝雀に入門したんです。師匠には本当にかわいがっていただきました。
木村☆私の記憶にある学生服姿の雀々さんは、その頃の姿だったんですね。師匠は厳しい人でしたか。
桂☆落語に関しては、非常に厳しい方でした。「まだあかん、まだあかん」と自分で納得できるまで追究する完全主義者で、趣味もまったく無く、落語一筋の人でした。でも落語以外の部分では、本当に、あたたかい、おおらかな方でした。
木村☆それにしても雀々さんが落語修業を始められた七〇年代は、いい時代でしたね。
桂☆関西制作のお笑い番組が、とにかく面白かったですね。八〇年代のマンザイブームへと繋がっていく勢いがありました。落語では、うちの師匠のブームも到来しました。
木村☆いまや、枝雀師匠の形容詞だった「爆笑王」といわれるほどの人気落語家になった雀々さん。入門から三〇年後の二〇〇七年には、やしきたかじんさんプロデュースの独演会「雀々十八番」を大阪のシアターBRAVA!で開催されて、六日間全席完売という快挙を成し遂げられました。私は六日目にうかがいましたが、千数百席が本当に満席で、爆笑の渦に包まれていましたね。
桂☆ありがとうございます。たかじんさんが僕の落語をご覧になって、応援してやろうとプロデュースしてくださったんです。後輩思いの優しい方で、感謝、感謝です。この「雀々十八番」は、僕にとって大きな転機になったんですよ。価値観も変わりました。二〇〇席、三〇〇席の寄席もいいんですが、もっと多くの方に見ていただくには一〇〇〇席以上の大箱でやる必要があります。落語家は現在、大阪で二五〇人、東京で五五〇人ぐらいが活動していますが、その中で何人が大箱で落語ができるかいうことです。「雀々十八番」はある意味、僕の勝負のときだったと思っています。

五一歳で東京進出
夢は日本武道館で還暦独演会
木村☆残念なことに、桂枝雀さんも、やしきたかじんさんも、そして桂米朝さんも亡くなられましたが、最後にお聞きしたいのは、五〇歳を超えて、なぜ、東京に拠点を移されたのかということです。大阪にいれば、それなりにポジションもあり、仕事もあったでしょう。どうしてなんですか?
桂☆うちの師匠がやっていないことは何かと考えたら、「これだな」と思ったんです。大阪に拠点を置いて東京に出ることはあっても、東京に住まいまで移して、東京を拠点に活動する上方落語家はいません。東京には例えば『笑点』(日本テレビ)の春風亭昇太さんや林家たい平さんがいたり、司会者としても活躍する立川志の輔さんがいたり、脂の乗り切った落語家がたくさんいます。僕は、東西のどの落語家協会にも属していない無所属の身ですから、誰とでも自由にコラボレーションができます。背景も価値観も違う人たちと一緒に仕事をすることで、きっと、新しい何かが生まれるにちがいないと思ったんです。ただ、四〇代で東京へ行くのはちょっと早すぎるし、六〇歳になってからでは遅い。五一歳がちょうどかなと思って米朝師匠がご存命中に「裸一貫になって勝負をかけます」とご挨拶して、お許しをいただいたんです。
木村☆雀々さんの落語もそうですが、上方落語は、とにかく大笑いしてすっきりして帰るもの。東京の落語って、折目正しいんですよね。笑うというより「粋ですね」「お上手ですね」とほめて帰る感じで、関西人としてはちょっと物足りなく思ったりします。これも、辻噺から始まった上方落語と、お座敷から始まった東京落語の違いなのかもしれませんが。
桂☆それはありますね。僕は東京に来て四年ですが、東京のお客さんはびっくりされるんです。こんなに大笑いしたのは初めてだとか、機関銃みたいな賑やかでスピード感のある落語は初めてだとか……。毎年国立演芸場で春、夏二回の独演会を開いていますが、最近は、お客さんもよく分かっておられて、爆笑を期待して来られる方が多いんです。東京は他県からも人が集まっており、密度が濃い。時間はかかるだろうけど、最終的には一〇〇〇席ぐらいの大箱で独演会を数多くやって、雀々落語を発信していければというのが、東京進出の第一目標なんです。うちの嫁さんも、ハイハイと賛成してくれ、一戸建ての家も手放して全部リセットして来たんですよ。
木村☆そうなると、東京オリンピックの頃にはきっと雀々ブームが沸き起こっていますね。
桂☆そのオリンピックの年に僕は六〇歳になります。僕の夢なんですけど、日本武道館で還暦独演会をやりたいんです。演目は「地獄八景亡者戯」。八〇〇〇人の観客の皆さんには全員、頭に三角頭巾をつけてもらい、亡者になってもらう。地獄を巡りながら大笑いしたり、怖がったり、噺の中にどっぷり浸かって、大いに楽しんでいただこうというわけです。
木村☆それは、いいですね! 楽しみにしています。今後も雀々落語を、日本中に発信していってください。本日はありがとうございました。

対談後記
「艱難辛苦、汝を玉にす」という言葉がある。逆境が人を育てるという意味であるが、この人が置かれたのは、並みの逆境ではない。母に去られ、無理心中を強いた父にも去られたのは、まだ中学一年生の時だったという。いくら周囲の温かい目があったとはいえ、良くぞここまで立派に育ったものだ。初めて見たとき「おサルさんみたいだ」と思った詰襟の少年に、こんな壮絶な過去があったとは知らなかった。そんな雀々さんが、五一歳を機に東京へ居を移し、さらには日本武道館での還暦独演会を目指すという。順境に留まらず、あえて再び逆境に身を置いた雀々さんに、最大限のエールを贈りたいと思う。「必死のパッチでがんばれ!」と。

桂 雀々(かつら・じゃくじゃく)
桂 雀々(かつら・じゃくじゃく)1960年、大阪市生まれ。落語家。本名:松本貢一。12歳のとき母親が蒸発し、1年後に父親も家を出たため中学生の3年間を一人で暮らす。一方、小学生時代からテレビの視聴者参加番組の常連として活躍し、14歳で落語に出合う。1977年6月1日、上方落語の桂枝雀に入門、同年10月、名古屋・雲竜ホール(現・ダイアモンドホール)の枝雀独演会で「浮世根問」で初舞台。2002年、上方お笑い大賞最優秀技能賞受賞。2007年、芸能生活30周年を迎え、やしきたかじんプロデュース及び出演の独演会「雀々十八番」を大阪のシアターBRAVA!で6日間にわたり開催。2010年、51歳を機に「五十歳五十箇所地獄巡り」を開始。2011年、拠点を東京に移し、全国で活動中。趣味は映画・演劇鑑賞、卓球、ゴルフ。特技は誰とでも馴染むこと。著書に過酷な少年時代を綴った『必死のパッチ』(幻冬舎)がある。